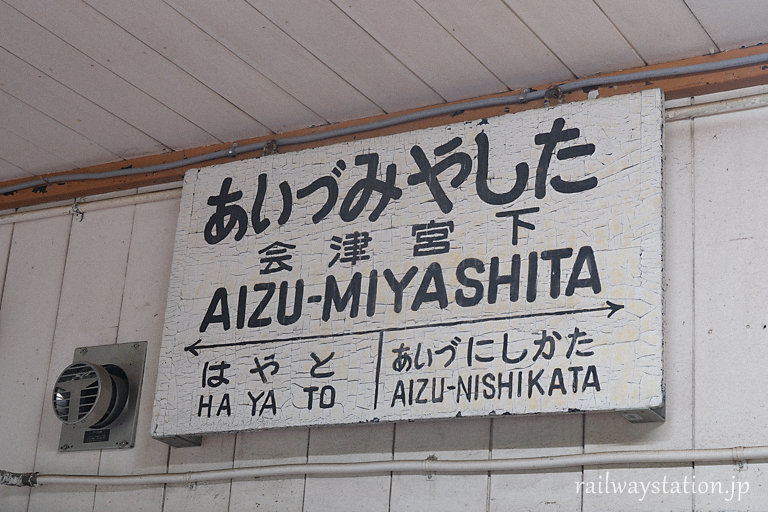三木城址近くの築堤横、街を見下ろす駅
鈴蘭台駅から粟生行きの列車に乗り、三木上の丸(みきうえのまる)駅で下車した。

築堤上のレールに合わせたプラットホームは一面一線。
副駅名は三木城址前。三木城は駅の南西側一帯にあった。
三木城は織田氏と別所氏の三木合戦で有名。織田方を率いた秀吉は三木の干し殺しと称される兵糧攻めを行い、城主一族を切腹に至らしめた。
ホームと反対側、木々の向こう側すぐの所に三木城跡上の丸公園がある。三木城址の北あたりになり、駅は上の丸と名付けられたのだろう。

高い位置のホームから町を見下ろせばお城から見ている気分。三木市中心街のやや外れと言った位置だろうか?
古さ漂う木造駅舎は嵩上げされ…

木造駅舎も線路の高さに合わせ、土台でかさ上げされ掲げられるように建っていた。それ以外、これと言って特徴的な造りがある訳では無いが、素朴な木造で趣感じさせる。駅の中に入るためには、急なスロープか階段を上がらなければいけないのはちょっと面倒…
三木上の丸駅の開業は、三木電気鉄道時代の1937年(昭和12年)12月28日。広野ゴルフ場前駅から当駅間の約5.1㎞延伸開業時の時で、当初の名称は三木東口駅と言った。駅舎はその頃からのものだろうか…?
駅名は1939年(昭和41年)に上の丸、1948年(昭和23年)に現在の三木上の丸に改称されている。

坂の下に下りてみると、道路沿いに立派な公衆トイレがあった。「神戸電鉄 三木上の丸駅」の看板を絶妙な位置にでかでかと掲げ、道路から見るとこっちが駅舎に見えてしまうだろう(笑)

坂の上の駅舎に戻ってきた。
嵩上げされた駅舎は2階建ての高さがある。下の部分は板で覆い隠され、奥は壁で見えず、今やどうなっているかわからない。何かあったのだろうか…?
ウィキペディアに載っている1955年以前という三木上の丸駅の画像を見ると、面白い事に気づいた。駅舎への出入口で、今は急なスロープとなっている部分が、昔はそうでなく、線路に並行して通路が伸びていたようだ。柵がある事から、それなりの高低差があり、柵の切れ目には、階段か梯子か何かがあったと思われる。
元々、その通路が下の道路あたりまで緩やかな坂となって続いていたのだろう。しかし駅周辺が造成され、従来の通路が無くなり、駅舎の真下にスペースが作られ、スロープや階段が出来たのでではないだろうか…?

駅舎出入口には小さな軒が取り付けられていた。木造らしくいい造りだ。

駅舎外観は白いクリーム色に塗られていたようだが、それも剥がれ、木の板張りが露出し古色蒼然さ溢れる。窓はサッシだが、重なるように木枠の部分があり、昔はそこが窓だったのだろう。

無人駅となり窓口は塞がれている。色々改修されているのだろうが、天井は木の板張りのまま。ポツンとはめ込まれた、小さな防犯カメラは、怪しい駅オタクに目を光らせている事だろう(笑)
床面はコンクリートだが、隅に四角い継ぎはぎのような部分があった。何かがあった痕跡なのだろう。同じ粟生線の三木駅旧駅舎には売店の跡らしきものが残っていたが、この駅にも売店でもあったのだろうか…?それかまさか駅舎の下の階に下りる階段を潰した跡とか!??

ホームに至るためには、更に締めの階段を上がらなければいけない。
新開地行きの列車が到着し。数名の人が下りてきた。

ホーム側から見る駅舎もなかなか渋い。一部が張り出した造りになってるが、水道管らしきものが壁から出ているので、水場があったのだろうか。
だけど築堤の高さには、駅舎とホーム以外の敷地は無く、周辺の土地も民家に取り囲まれごくわずか。スペースに余裕はほどんど無く、将来、駅舎が取り壊される事になったら大変そうだ。
通常、駅舎を取り壊す時、駅敷地内に仮駅舎や別の動線を作って対応する。もちろんこの駅も、そう言ったものを作ろうを思えば作れるのだろうが、敷地が狭い上、築堤のレールに合わすとなると、手間な分、費用も掛かりそうだ。それが三木上の丸駅の駅舎が、木造のまま残っている理由なのかもしれない。
なので取り壊しの時は、工事期間中、駅の休止もあり得そうだ。もちろんレトロ駅舎好きとしては、そんな時なんか来なく、この木造駅舎がずっと高く掲げられる姿を見ていたいものだ。

ホーム上の木造上屋も相当に年季が入っていた。

今度は粟生行きの列車が坂を下り入線してきた。

約半世紀前の1970年あたりに製造された1100系電車に、古レールが支え使い込まれた木のベンチがある待合所、そして木造駅舎。何とレトロで味わいのある粟生線の風景か…
[2025年(令和7年)10月](兵庫県三木市)
- レトロ駅舎カテゴリー:
 私鉄の二つ星レトロ駅舎
私鉄の二つ星レトロ駅舎